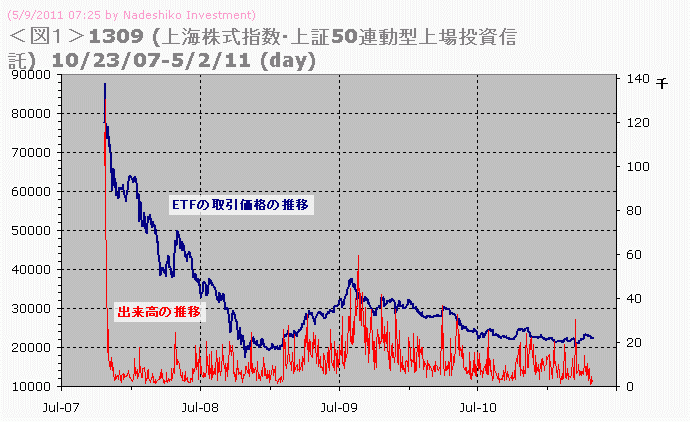
5月12日、東証に新たなETFが2つ上場します。
1つは、タイ株式市場のインデックス「SET50」連動型。もうひとつは、マレーシア株式市場のインデックス「FTSEブルサ・マレーシアKLCI」連動型で、設定・運用はいずれも野村アセットマネジメントです。
ETFといえば、そのメリットとして「インデックスに連動しているのでわかりやすい」「最低売買単位が小口なので、少額から買える」「個人では参加しにくい海外市場などにも投資できる」「板状況を見ながら場中いつでも売買できる」といった点などがよく指摘されます。
この2本のETFも、最低投資単位はタイSET50連動型が2000円程度、マレーシアKLCI連動型は4000円程度(いずれも1口単位)。その少額資金で、東南アジアの株式市場という、個人ではなかなか直接参加しにくいマーケットに参加できるのですから、確かにこれは大きなメリットといえます。
ただ、ETFのメリットはそればかりではありません。非常に大きい特徴は、ETFは貸借銘柄であり、しかも、新規上場したその日から信用取引で売り買いともに可能である、という点です。
個別銘柄の場合、一般信用取引を利用すれば上場初日でも信用買いはできますが、ほとんどの場合、信用売りはできません。個別銘柄ではできない「上場初日からショート」がETFはできるのです。
「上場初日からショートできて、何かいいことでもあるのか」と思うかもしれません。
この「上場初日からいつでもショート可」の活用法としては、まず、たとえば同じ市場を投資対象とした投資信託を持っている場合には、そのヘッジとしていつでも使えうことができます。タイやマレーシア市場に限らず、東南アジア諸国に投資するファンドならば、この新規上場のETFがヘッジに利用できそうです。
さらに、そもそもETFが組成される背景は何かを考えてみると、もっと積極的な売買対象として使える可能性に気付きます。
日本市場にETFが初めて登場したのは2001年7月でした。金融不安再燃の懸念、持ち合い解消売りが市場を押し下げる重い要因となっていた時期です。
そのときの市場活性化策のひとつがETFだったのですが、これは、ETFの上場によって市場を盛り上がらせようというよりも、持ち合い解消売りの受け皿という意図が強くあったことは間違いありません。
大量の持ち合い解消売りが市場で直接行われれば、株価の下落に拍車がかかってしまいます。しかし、大量の売りたい株式を証券会社なり運用会社なりが買い取り、買い取った株式でETFを組成して上場すれば、大量の売りで株式市場を下落させることなく、売りたい投資家は売ることができます。
つまり、ETFが組成される背景のひとつとしては、売りたい投資家が多いものの、直接市場では売りにくい、という状況が考えられるわけです。
実際、当時は銀行株の売られ方がひどかったことから、財務大臣だった“塩爺”が、日経平均連動型やTOPIX連動型に続いて「銀行株ETFを作れ」と号令を掛けていました。
ETFの組成が「売りたい投資家が多い状況」を示唆するものであるならば、新規上場のETFを買うことは、その相場局面の趨勢に逆らうことになります。趨勢に乗るのであれば、新規上場のETFは「売り」が正解です。
ちなみに、全くの偶然でしかありませんが、ETFが初上場した約2ヶ月後、“9.11”で市場は大暴落しました。もし上場当初に日経平均連動型なりTOPIX連動型なりのETFをショートしていたとしたら、それによって資産の目減りを幾分なりともカバーできたに違いありません。
「売りたいが、市場では売りにくい」という状況は、持ち合い解消売り以外でも生じる可能性があります。
たとえば、03年から07年半ばにかけて世界的に相場が好調な時期、BRIC‘sをはじめとする新興国の市場は実に勢いがありました。そうした成長市場に対しては、機関投資家など大口資金も無関心ではいられなかったはずです。
その場合、直接投資するよりもその市場を対象とした投資信託を購入するケースも多々あると思われます。
かくして、新興国市場を運用対象とした投資信託は大口投資家の資金が入り、資産額を伸ばすことになりますが、その市場に陰りが見え始めたとき、そうした大口投資家はいち早く逃げようとするものです。
その大口の解約に対しては証券会社がそのファンドを一旦買い取り、解約の代金を支払います。
もし、大量の解約要請が出たとすれば、運用会社としてはファンドに組み入れている投資対象を市場で売らざるを得なくなるでしょう。しかし、規模の大きくない新興市場で大量の 売りを出せば、それによって市場は暴落しかねません。
このようなケースでも、その市場を対象としたETFが組成されることが考えられます。買い取ったファンドに組み入れられている投資対象で新たにETFを組成して日本市場に上場すれば、その市場に直接売りに行く必要もなく、そのETFを買 いたい投資家に投資対象を転売することができるわけです。
こうした背景で組成されたETFがあるとすれば、それもまた、「売りたい投資家が多い」という趨勢下で上場することとなります。その趨勢に乗ろうとするならば、「上場当初からショート」が最有力手段です。
ここで、2007年以降に上場したETFの例をいくつか見てみましょう。
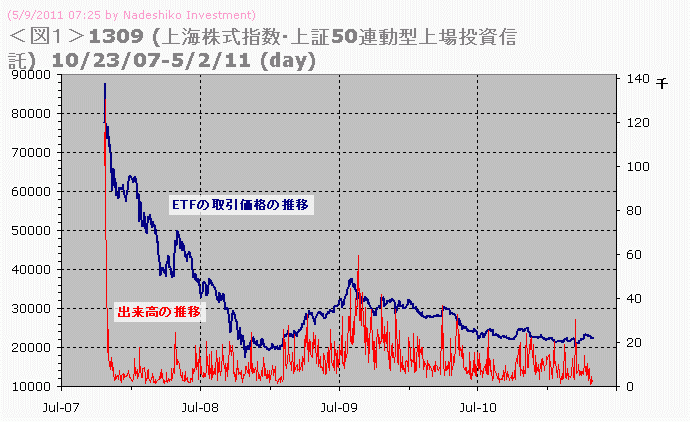
図1は2007年10月上場。サブプライムローン問題が表面化して国内外の株式市場が大きく下げた後、短期的なリバウンドにも限界感が見えてきた頃です。
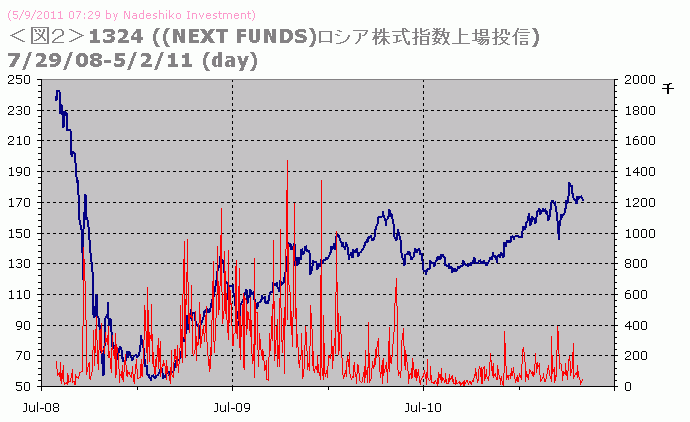
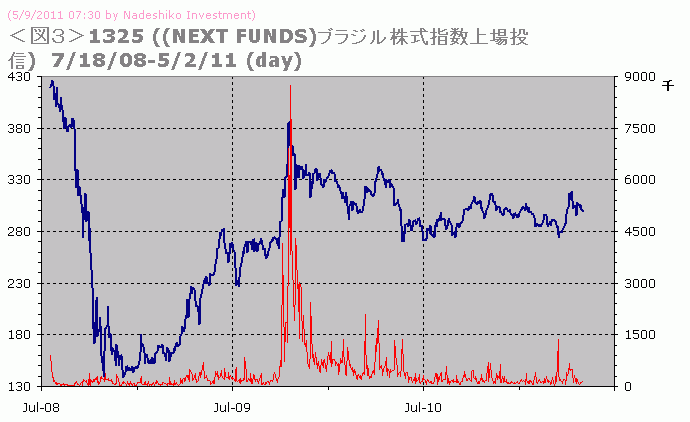
図2と図3は、いずれも2008年7月の上場で、米国ではとくに銀行株に対する懸念が強まっていた時期。図4は上場が2008年9月。この図4と同じ頃、いまでは上場廃止となっていますが、通貨連動型のETFも上場しています。対象通貨は、ロシア・ルーブル、ブラジル・レアル、トルコ・リラという3種類の新興国通貨でした。
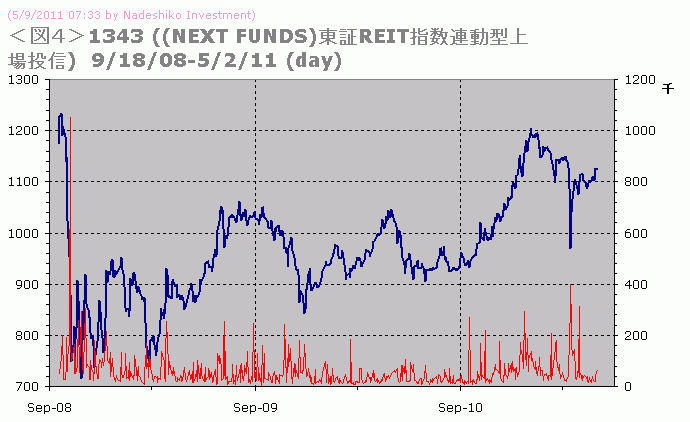
これも全くの偶然でしかありませんが、図2、図3、図4のETFが上場した直後、“リーマン・ショック”で世界中の株式市場が暴落し、また、世界中の投資対象が投げ売られる中、唯一「円」だけが買われました。そのため、いずれも上場当初からETFの 価格は急落です。
1はそれよりも1年弱早い上場でしたが、上海市場はまさに07年10月が高値で、以後下げ続けています。やはりこのETFの価格も上場直後から急落です。
結果論ではありますが、いずれかのETFでもショートしていたら、リーマン・ショックの大暴落で目減りする資産が幾分なりともカバーできたであろうことは言うまでもありません。
もっとも、ETFが組成される背景は他にもいろいろあると思われますから、「いつでも何でも上場当初にショートすれば確実に儲かる」ということでは決してありません。
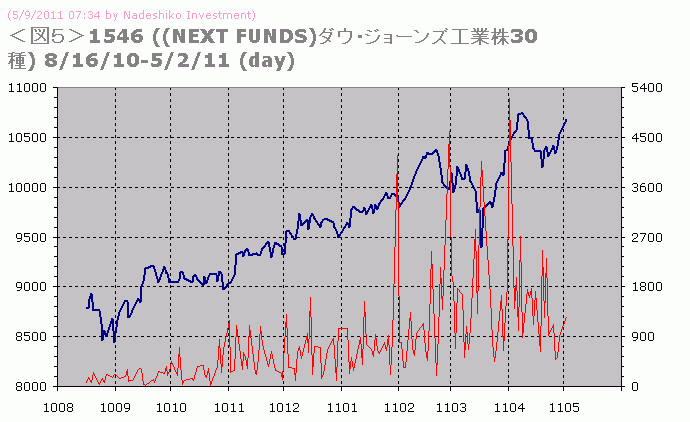
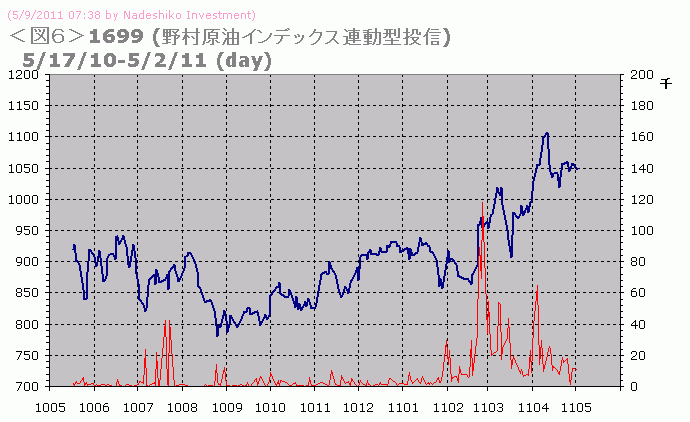
図5のNYダウ連動型ETFのように、上場から着実に値を上げているものもありますし、図6の原油インデックス連動型は、上場当初はやや弱い動きだったものの急落というほどのこともなく、 その後はむしろ強い動きになっています。
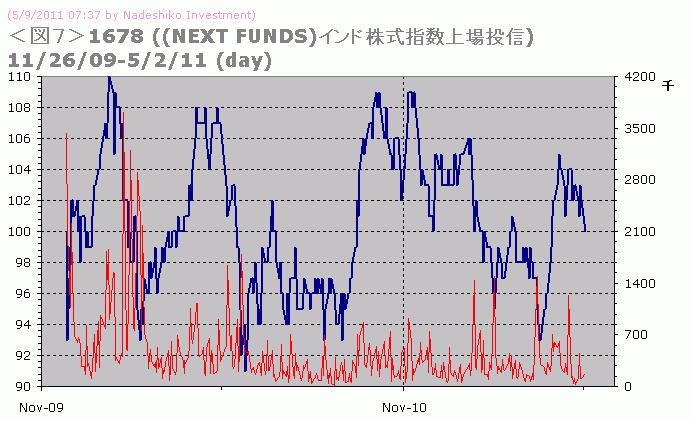
また、図7のインド株式指数連動型は、価格の水準自体が安いことも一因と見られますが、上場から上下を繰り返す動きを続けています。
「上場初日からショートできる」というETFならではの特性を活かすうえでは、何故そのETFがいま上場するのか、投資対象の国や市場の動向からして「売りたい投資家」が多い状況かどうかをよく考えてみることが重要です。
12日に上場するタイやマレーシアの状況はどうかといえば、いずれも中国人の影響が大きい経済です。その中国は、2009年に北京オリンピックのあった2008年をはるかに上回る強烈な金融緩和政策を行い、強い経済成長を実現していましたが、その反動が物価高騰という形で現れています。そのため、インフレ圧力を押さえ込もうと、現在、金融引き締めを強化しているさなかにあります。
タイとマレーシアも、おそらく、中国の“ジャブジャブ”政策の波及効果が大きいと思われますが、2009年、2010年と経済は非常に好調でした。が、やはりインフレ圧力が強まり、両国ともに金融引き締めを強化しています。
タイでは、今年1月と3月に2回の利上げを行い、マレーシアはつい先日、5月5日に今年初の利上げを発表したばかりです。
株式市場に目を転じれば、過去2年の好調だった経済を反映して過去5年の高値圏にあります。
タイの株価指数SET50の場合は、石油関連銘柄のウェイトが非常に高いため、これまでの原油高が寄与していた面もありそうですが、逆に、この先、原油をはじめコモディティ市場が軟調になれば、その影響を受ける可能性は否めません。
マレーシアも産油国ですから、原油市況の影響を考える必要があるでしょう。
と、このように言うと、いかにも「売ったほうがいいぞ」という主旨に感じられるかもしれませんが、ここでの記述は間違っても売り推奨ではありません。ただ、新種のETFが上場するときには、それをもてはやす向きが現れることがしばしばあります。それにまんまと乗っかって上場当初にすっ高値で買ってしまうことだけは避けたいところです。
今回の新規上場ETF2本に関しては、長期的な成長が期待できるとしても、まずは直近の利上げの影響を見極めてから買い出動しても遅くはありません。現状、「買い」は慎重姿勢のほうがよいのではないでしょうか。
他方、新興国のインフレ圧力や商品市況に対して懸念を持っている人であれば、売る候補の対象銘柄のひとつになると思います。
なお、ETFは最低投資単位が少額であるため、ある程度まとまった額を信用取引で売買するとなると建玉の口数が大きくなります。信用取引では、新規建てから1ヶ月ごとに管理料が単元数単位でかかってきますから、取引する口数によっては、かなりのコスト高になる可能性があります。その点は十分気をつけてください。
Top に戻る