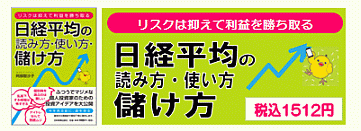【異常ボラ局面】その極端な値動きを利益に変える3つの方法<3>
近年の異常ボラティリティー局面の理由は何か
11月15日付けの当欄で、市場全体の「大急落→乱高下」を利益に変える方法を考えてみました。この「大急落→乱高下」とは、要は、市場が荒れに荒れまくって、株価のボラティリティー(変動率)が極端に高まっている状況です。
ボラティリティーについては時折当欄でも取り上げていますが、改めて、ボラティリティーが極端に高まるのはどういう局面なのか。過去の日経平均先物とボラティリティーの推移を見てみましょう。
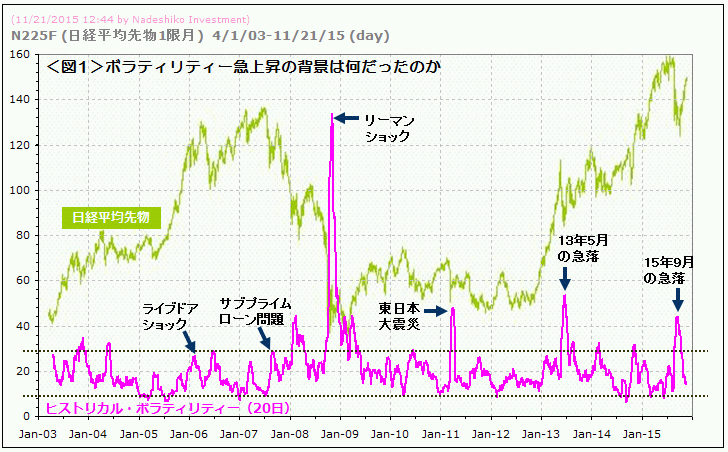
図1は、日経平均先物の20日分のデータ(引値ベース騰落率の標準偏差)を年率換算したボラティリティーの推移です。平常は概ね20±10%程度のレンジで動いていますが、株価が急落しているときにはこのレンジを上に突破したり、時には、突拍子もない爆騰にもなっています(株価が大幅に上昇する局面は、「株価が大きく動いている」とはいっても、一本調子で大上昇を何日も続けることは滅多にないため、ボラティリティーはさほど上昇しません)。
ボラティリティーが突拍子もなく急上昇する背景については、一般的に「重大なショックイベントが起きたとき」と言われます。確かに、大震災しかり、“リーマン・ショック”しかり。それ以前では、たとえば米国で同時多発テロが起きた01年9月11日の翌日にボラティリティーが急上昇しています。
「何らかのショックが起きて株価が急落し、乱高下した結果、ボラティリティーが急騰する」というのは、今さら言われるまでもない、当たり前のことだと思うかもしれません。では、たとえば13年5月、大震災時を上回るボラティリティー高騰となっていますが、このときどんなショックがあったのでしょうか。あるいは、15年8月から9月にかけても大震災時に迫る高ボラティリティーとなっています。このときは、上海市場の混乱による市場急落が原因ではありましたが、大震災に匹敵するようなショックだったのでしょうか。
前回の上昇相場を振り返れば、ライブドアショックやサブプライムローン問題の表面化など、ショックによって株価が急落した局面は何度かありました。ただ、そのときのボラティリティーの上昇はレンジの上限で止まっています。それに比べて、今回の上昇相場はどうでしょう。ショックがあろうがなかろうが、ショックの内容が何であれ、日経平均先物(および日経平均株価)が急落して中トレンドレベルでの下落基調が始まると、ボラティリティーはレンジを上抜けして、13年5月や15年8月は急騰するところとなっています。
なぜそうなるかと言えば、先物が急落すると、何の抵抗もなくいくらでも下げる。市場全体も一斉に下げる。しかも、その下げ方の速度が極めて速くなっているからでしょう。13年5月23日の爆落などは、明らかなショックがあったわけでもないにも関わらず、先物は一時ストップ安まで下げています。そんな状況ともなれば、市場全体が混乱し、ボラティリティーが急上昇するのは必然の成り行きとも言えます。つまり、近年の市場にとっての「重大なショックイベント」とは、理由はともあれ、「とにかく先物が急落すること」と考えてよいのではないでしょうか。
方法その3「『日経平均オプション』でボラティリティーをもらう」
ボラティリティーは、リスクの大きさを表す指標です。高ボラティリティー局面はハイリスク、ということですが、と同時に、それは短期間で高いリターンが得られる局面でもあります。先物主導と高速取引がもたらす極端な値動きを利益に変える方法の3つ目は、この高ボラティリティー局面をチャンスにすること。これを端的に狙える取引が「日経平均オプション」です。
先物が大きく下げる局面で利益をあげる方法としては、先物・ミニ先物やレバレッジ型ETFをショートする、もしくは、ダブルインバース型ETFをロングする、という方法ももちろんあります。しかし、その高ボラティリティー局面における日経平均オプション取引の醍醐味たるや、これらの比ではありません。というのは、第一に、日経平均オプションのストップ高水準が極めて高く設定されているからです。
日経平均オプションの値幅制限は4半期ごとに見直されますが、現行の水準(9月から11月末までの取引に適用)は「前日の終値+2240円」。権利行使価格が日経平均株価よりも非常に安く、価格が1円、2円、3円という“ほとんど無価値”のプット・オプションでも、ストップ高は「+2240円」です(ただし、オプション価格が1000円超になると呼値が10円単位となります)。価格2円のプットを1枚、2000円で買ったとすれば、それがその日のうちに224万円にもなり得る。1日内に1000倍以上のリターンが得られるポテンシャルを秘めている、ということです。この超絶ハイリターンのポテンシャルは、先物にも個別銘柄にもありません。
もっとも、オプション価格がストップ高するような状況はまず起こらないと思われますが、たとえば8月19日から日経平均が急落した局面では、数円で取引されていたプット・オプションの価格がわずか数日のうちに100倍、150倍、あるいは200倍超になった例が続出しています。1日で価格が5倍になろうが、10倍になろうが、100倍になろうが、ストップ高はそれよりもはるか上ですから、何の咎めもないわけです。
高リターンのカギは「インプライド・ボラティリティー」にある
日経平均オプションの価格は、原資産である日経平均株価とオプションの権利行使価格、期日までの残存日数、そして過去の値動きに基づくボラティリティー(ヒストリカル・ボラティリティー)などの要素によって理論値を計算することができます。ただ、実際の取引価格は需要と供給によって決まりますから、理論値通りにはなっていないのが普通です。
たとえば、8月24日の引け後のナイトセッションで日経平均先物は1万7160円の安値をつけています(時系列データでは25日の安値)。25日の引値ベースのヒストリカル・ボラティリティーは、この下落局面最大の47.%。この数字をもとに、権利行使価格1万6000円の9月限プット・オプション(期日までの残存日数17日)の理論値を計算すると、244円になります。
ところが、実際の9月限・権利行使価格1万6000円のプットがこの日のナイトセッションでつけた高値は505円。理論値よりも2倍以上高く買われています。なぜ理論値よりもそんなに高い値段がついたのかといえば、日経平均がもっと下がるのではないか、という思惑が強く働いたためです。
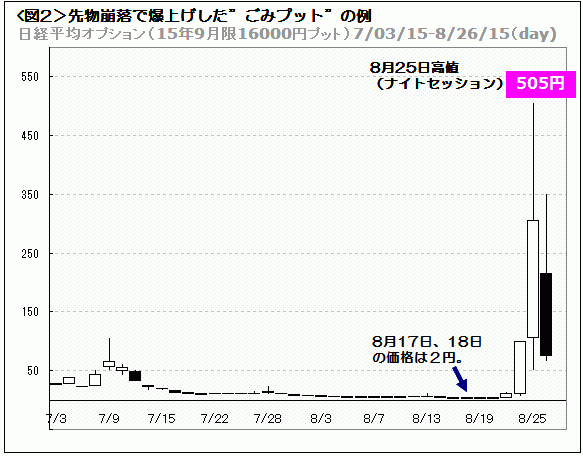
権利行使価格1万6000円のプットは、期日の日経平均株価のSQ値が1万6000円より安くなっていた場合に「(1万6000円−SQ値)×買い枚数×1000」相当額を受け取ることができる権利です。期日の日経平均株価が1万5500円だとしたら、権利行使価格1万6000円のプットを1枚買っていれば、受取額は「500円×1枚×1000円」の50万円。期日の日経平均株価が1万4000円まで下がっていようものなら、「2000円×1枚×1000」で200万円もの金額を受け取ることができます。ただし、期日のSQ値が1万6000円以上ならば、権利を行使しても意味がないので、このオプションの価値はゼロ。オプションを買った際の支払い額はまるまる損失となります。
そうすると、期日より前の時点で、日経平均株価が権利行使価格よりも高い水準にあっても、「日経平均はもっと値下がりして、期日には1万6000円より安くなっているのではないか」と予想する人が多いほど、1万6000円で売れる権利をいまのうちに買っておけ、という需要が増え、オプション価格も値上がりしていきます。これは、市場参加者の思惑によって、理論値の計算上に用いるヒストリカル・ボラティリティーよりも取引価格に織り込まれているボラティリティーのほうが高くなっている状況です。
この市場参加者の思惑によって取引価格に反映されているボラティリティーは、インプライド・ボラティリティーと呼ばれ、その値は取引価格から逆算することができます。「先物が1万7160円のとき、9月限の権利行使価格1万6000円プットが505円」というデータから逆算すると、このときのインプライド・ボラティリティーは68.6%という高さになっています。
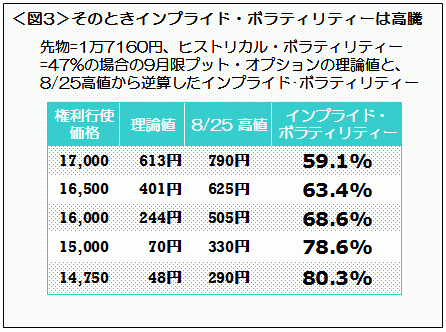
先物の下落に歯止めがかからず、日経平均はどこまで下がるかわからない、という市場参加者の恐怖心が募るほど、インプライド・ボラティリティーは上昇し、プット・オプションの価格も値上がりします。わずか数円しかなかったプットのオプション価格が数日で100倍、200倍にもなるのは、日経平均の下落の大きさもさることながら、このインプライド・ボラティリティーの上昇が大きく関係しています。つまり、インプライド・ボラティリティーが上昇する局面は、100倍、200倍という超ハイ・リターンもあり得る絶好機だということです。
しかも、権利行使価格がその時点の日経平均株価よりも低い(オプション価格も安い)プット・オプションは、先物が下げ始めた段階ではほとんど反応しないケースがあります。8月の急落の例でいえば、権利行使価格1万6000円のプットは8月20日まで2円、3円という価格で取引されていました。そのときの日経平均株価は2万円を超えていましたから、当初は「まさか日経平均株価が1万6000円割れする」などと予想する参加者は少数派だったのでしょう。ところが、先物が下落幅が拡大したことから、「日経平均1万6000円割れ」が徐々に現実味を帯び、オプション価格は21日に11円、24日には100円に上昇。25日の高値が先述の通り505円です。
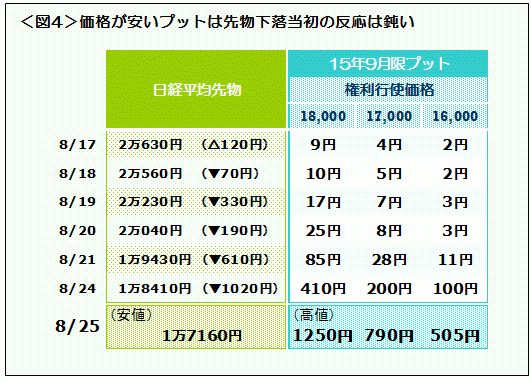
先物・ミニ先物、レバ型ETFをショートする場合、急落の当初で売ることができなかったとすると、「いまから売っても遅いのではないか」等々、取れる値幅の縮小と踏み上げのリスクを心配してショートできないケースもあると思います。その点、プット・オプションは、急落当初に買えなくても、まだ安いプットもあると予想されます。また、日経平均の値下がりが続けば、より安い権利行使価格のプット・オプションが追加設定されますから、多少出遅れてもチャンスはあるはずです。
さらに、仮に買ったところが目先の底で、期日に向けてオプション価格が下がったとしても、損失はオプションを買ったときに支払う金額に限定されます。2円のプットを1枚買った場合なら損失は最大2000円。3円のプット1枚なら損失は最大3000円です。その一方で、先物の下落が止まらなければ、リターンは何十倍、何百倍にもなる可能性があるのですから、これこそまさに、極端な値動きをする相場を利益のチャンスに変えるうってつけの方法ではないでしょうか。
「日経VI指数」で市場参加者の心理を探る
先述したように、オプションのインプライド・ボラティリティーは、市場参加者が先行きの株価急落(暴落)を予測・警戒する状況になると上昇します。そのため、インプライド・ボラティリティーを指数化したデータは、市場心理を探る指標としても活用されています。
よく知られているのは、“恐怖指数”と称される米国のVIX(Volatility Index)です。これは、S&P500のオプションのインプライド・ボラティリティーを指数化したもので、この指数を原資産とする先物の指数に連動するタイプのETFは、日本市場にも上場されています。
日本では、日本経済新聞社が、期日まで1か月の日経平均オプションのインプライド・ボラティリティーを指数化した「日経ボラティリティー・インデックス」(日経VI)を算出・公表しています。
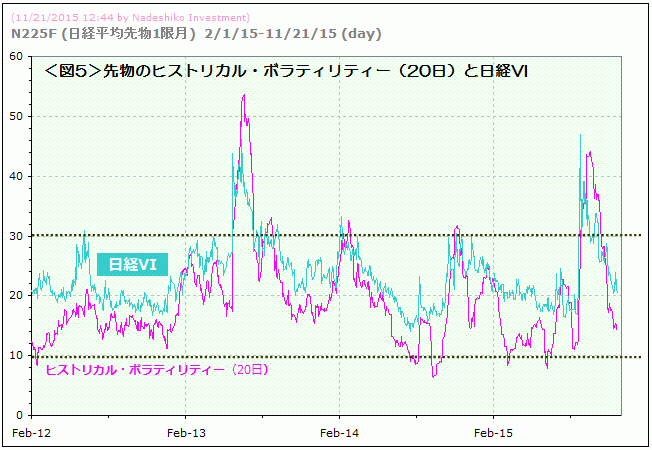
図1で見たヒストリカル・ボラティリティーの推移と比べてみると、まず、日経VIのほうがピークをつける時期が若干早いことがわかります。実際の市場よりもオプション価格のほうが先に株価の変動を織り込みにいっているということでしょう。また、レンジ内の動きにあるところでは、ボトムの位置がヒストリカル・ボラティリティーよりも高くなっています。市場の急落に対する警戒感が常にあって、とくにプット・オプションの価格が理論値よりも高めになる傾向があることが一因と見られます。
日経VIのデータは、日本経済新聞社のサイトでダウンロードできます。日経平均オプションに興味のある人はもちろんのこと、実際に取引しない人でも、この指数の推移は市場の心理を知るうえで大いに参考になると思います
ちなみに、日経平均のボラティリティーを対象とする「日経平均VI先物」、VI先物指数に連動する「日経平均VI先物指数ETN」(2035)が上場されているので、日経平均オプションのボラティリティーだけを売買することも可能ではあります。ただ、どちらも日々の取引は超閑散状態。米国のVIX先物に連動するETFが活況であることを考えれば、日経VI先物やETNにも将来性はあると思いますが、残念ながら現状は、取引するには難がありすぎ、と言わざるを得ません。
最後に、日経平均オプションについてひとつ付け加えておくと、今回は高ボラティリティー局面でハイリターンが狙えるプット・オプションの「買い」を取り上げましたが、実は、この局面の後にもまた別の利益のチャンスがあります。過去のヒストリカル・ボラティリティーおよび日経VI指数を見るとわかりますが、ボラティリティーが爆騰した後には急落があり、いずれは元サヤ的にレンジ内の動きに戻っています。この局面では、過剰につきすぎたプレミアムが剥げ落ちて、オプション価格は着々と下がっていきます。つまり、この局面はオプションの「売り」で利益を狙いやすいということです。
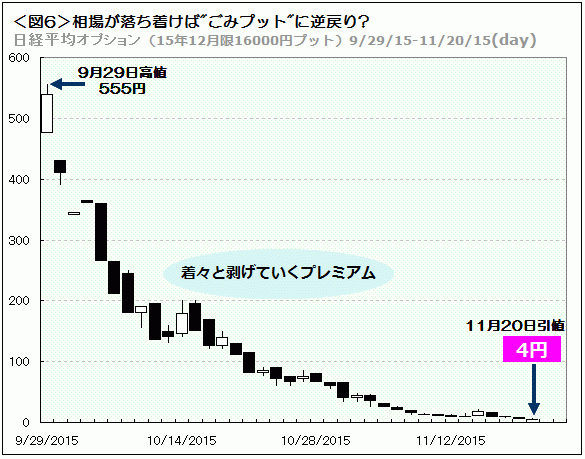
オプションの「売り」は、証拠金を差し入れる必要があるなど、取引対象は同じながらも証拠金不要の「買い」に比べて複雑な面があります。加えて、オプションの「買い」が「損失限定、利益の可能性は青天井(に近い)」であるのとは反対に、オプションの「売り」は「利益は限定、損失の可能性は青天井」です。このリスクの大きさがゆえに、「売り」のサイズの上限を厳しめに設定しているネット証券も少なくありません。
ただ、オプションの「売り」は、高い確率で利益を手にできるという非常に大きなメリットがあります。高ボラティリティーが沈静化していくプレミアム剥落局面では、その確率がより一層高まることが期待できます。先物の値動きが荒れまくっている渦中でも、さらに、その後に至っても、日経平均オプションはそれぞれ大きな妙味を提供してくれます。先物が極端な動きを見せ始めたときには、是非とも注目したい取引対象です。
↑ Top に戻る